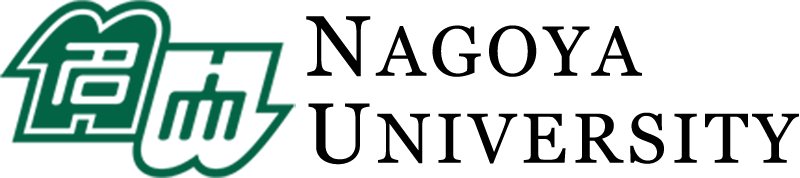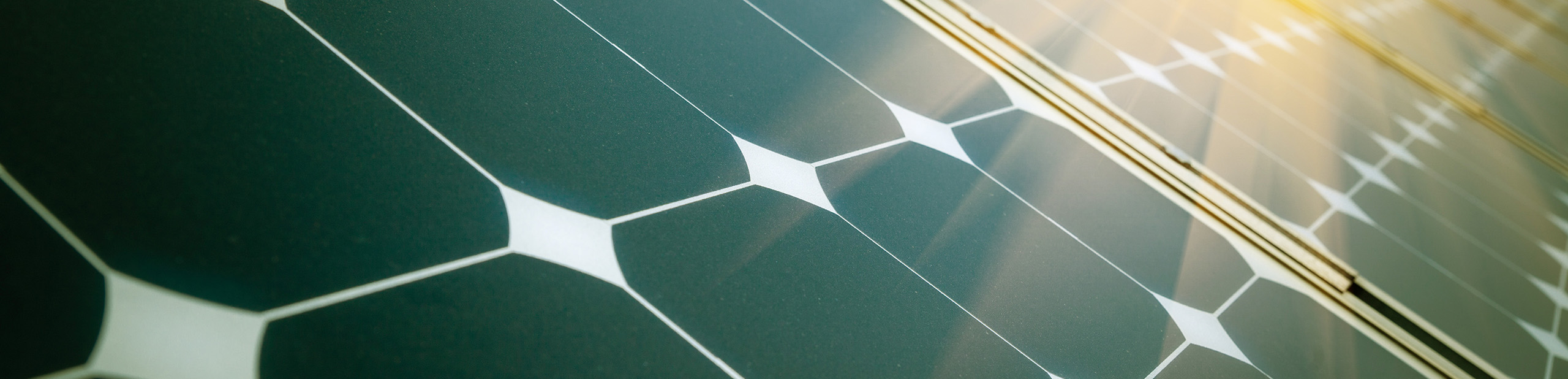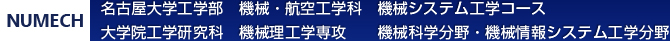Graduate Department of Mechanical Systems Engineering
News
About MSE
Since the Industrial Revolution, mechanical engineering has continued to evolve rapidly. Today, our daily lives face various societal challenges, such as the electrification and automation of vehicles, the widespread adoption of AI systems, and the urgent need for a decarbonized society—issues that cannot be resolved by individual mechanical components alone. Addressing these challenges requires approaches from both hardware and software perspectives, which is the role of mechanical systems engineering.
The Mechanical Systems Engineering program at our university is dedicated to advancing research and education in this field, contributing to societal transformation and problem-solving. The program consists of two main areas: the Mechanical Science and Engineering Division, which is based on the four core mechanics (thermal, fluid, material, and mechanical), and the Mechanical Intelligence Division, which integrates multiple mechanical elements, such as mobility and robotics, to design efficient systems. Each research group produces world-class academic achievements in their specialized fields, creating groundbreaking theories and practical solutions to address societal challenges. Additionally, through collaboration with domestic and international research institutions, the program seeks to drive disruptive innovation.
In terms of education, the program aims to foster innovative technological development and problem-solving skills by integrating mechanical engineering with systems engineering. Through hands-on projects and research opportunities, students learn to devise creative solutions for real-world problems, equipping them to meet the demands of a rapidly changing world.

Prof. Tsuyoshi Inoue, Department Chair