■ 名古屋大学の Boeing 社との関わり
名古屋大学では,The Boeing Company(以下 Boeing 社)から Grant を受け,次世代の航空宇宙工学・産業を担う工学者・技術者育成を目指した取り組みを行っています.特に,学生が主体となった航空宇宙工学に関連する活動の支援や,Boeing 社から提供されるインターネットを介した遠隔講義からなる Boeing Externship Program への参加を行っています.
■ お知らせ
| 2024年4月8日 | Boeing Externship 2024 への参加者募集を開始しました. |
|---|---|
| 2023年9月25日 | Boeing Summer Seminar 2023(於 東北大学)に参加しました. 詳細はこちら. |
| 2023年7月13日 | Boeing 社からの Grant を使用した航空機教育の一部として,藤野道格氏(Honda Aircraft Company 顧問(前CEO))による講演会を以下の通り開催します. 【定員に達したため,申し込み受付を終了いたしました.】 日時:2023年10月27日(金)9:00-12:00 詳細・申込み:こちらをご覧ください(申込期限:10月23日). |
| 2023年7月5日 | 2023年は5件の学生プロジェクトへの支援が決定しました.詳細はこちら. |
| 2023年5月22日 | 2022年採択プロジェクトの報告会を行いました.発表資料はこちら |
| 2023年4月6日 | Boeing Externship 2023 への参加者募集を開始しました. |
| 2022年7月1日 | 2022年は5件の学生プロジェクトへの支援が決定しました.詳細はこちら. |
| 2022年5月13日 | Boeing Externship 2022 が開始されました. |
| 2022年1月21日 | 飛行性能評価風洞を使用した飛行実習講義を Boeing 社の方々にご見学いただきました.当該施設の整備には Grant の一部も使用されています. |
| 2021年9月17日 | Boeing Summer Seminar 2021(オンライン)に参加しました. 詳細はこちら. |
| 2021年5月14日 | Boeing Externship 2021 が開始されました. |
| 2020年12月4日 | Boeing Summer Seminar 2020(オンライン)に参加しました. 詳細はこちら. |
| 2020年10月9日 | Boeing Externship 2020 が開始されました.COVID-19 の影響により,今年度は時期をずらしての開催となりました. |
| 2020年2月18日 | 2020年は3件の学生プロジェクトへの支援が決定しました.詳細はこちら. |
| 2020年1月9日 | 2019年採択プロジェクトの報告会を行いました.発表資料はこちら. |
| 2019年9月6日 | Boeing Summer Seminar 2019 (於 Centrair 中部国際空港)に参加しました. 詳細はこちら. |
| 2019年4月26日 | Boeing Externship 2019 が開始されました. |
| 2019年1月26日 | 2019年は2件の学生プロジェクトへの支援が決定しました.詳細はこちら. |
| 2018年12月26日 | 学生プロジェクト支援について,2018年採択プロジェクトの成果報告会を行いました.発表資料はこちら. |
| 2018年9月21日 | Boeing Summer Seminar 2018 (於 東北大学)に参加しました.詳細はこちら. |
| 2018年4月27日 | Boeing Externship 2018 が開始されました. |
| 2018年4月2日 | Boeing Externship 2018 の参加者の募集を開始しました(締め切りました). |
| 2018年1月22日 | 2018年は5件の学生プロジェクトへの支援が決定しました.詳細はこちら. |
| 2017年12月13日 | 2017年採択プロジェクトの報告会を行いました.発表資料はこちら. |
| 2017年9月8日 | Boeing Summer Seminar 2017 に参加しました.詳細はこちら. |
| 2017年4月28日 | Boeing Externship 2017 が開始されました. |
| 2017年4月3日 | Boeing Externship 2017 の参加者の募集を開始しました(締め切りました). |
| 2017年1月17日 | 2017年は4件の学生プロジェクトへの支援が決定しました.詳細はこちら. |
| 2016年12月13日 | 2016年採択プロジェクトの報告会を行いました.発表資料はこちら. |
| 2016年9月9日 | Boeing Summer Seminar 2016 に参加しました.詳細はこちら. |
| 2016年4月22日 | Boeing Externship 2016 が開始されました. |
| 2016年4月1日 | Boeing Externship 2016 の参加者の募集を開始しました(締め切りました). |
| 2016年1月9日 | 2016年は4件の学生プロジェクトへの支援が決定しました.詳細はこちら. |
| 2015年12月9日 | 2015年採択プロジェクトの報告会を行いました.発表資料はこちら. |
■ Boeing Externship
Boeing Externship Program では,北海道大学,室蘭工業大学,東北大学,金沢工業大学,東京大学,東京都立大学,岐阜大学,中部大学,名古屋大学,大阪公立大学,九州大学,久留米工業大学の学生とともに,Boeing 社から提供される web 講義により,航空宇宙工学・産業の現状や Boeing 社の取り組みについて学びます.
一連の講義ののち,Boeing Summer Seminar において参加学生が一堂に会し,各大学毎に選択した航空宇宙に関連したテーマについてプレゼンテーションを行います.講義,質疑,ディスカッションは基本的に英語で行われます.

2024年の Externship は下記の日程で開催予定です.
- 5月10日(金) 10:30-12:00
- 5月24日(金) 8:00-9:30
- 6月 7日(金) 10:30-12:00
- 6月21日(金) 10:30-12:00
- 7月 6日(金) 10:30-12:00
2023年度 Boeing Summer Seminar
2023年度の Boeing Summer Seminar は東北大学で開催されました.名古屋大学からは4名のチーム(前期課程2年生,1年生,学部4年生,3年生)で参加し,発表を行いました.
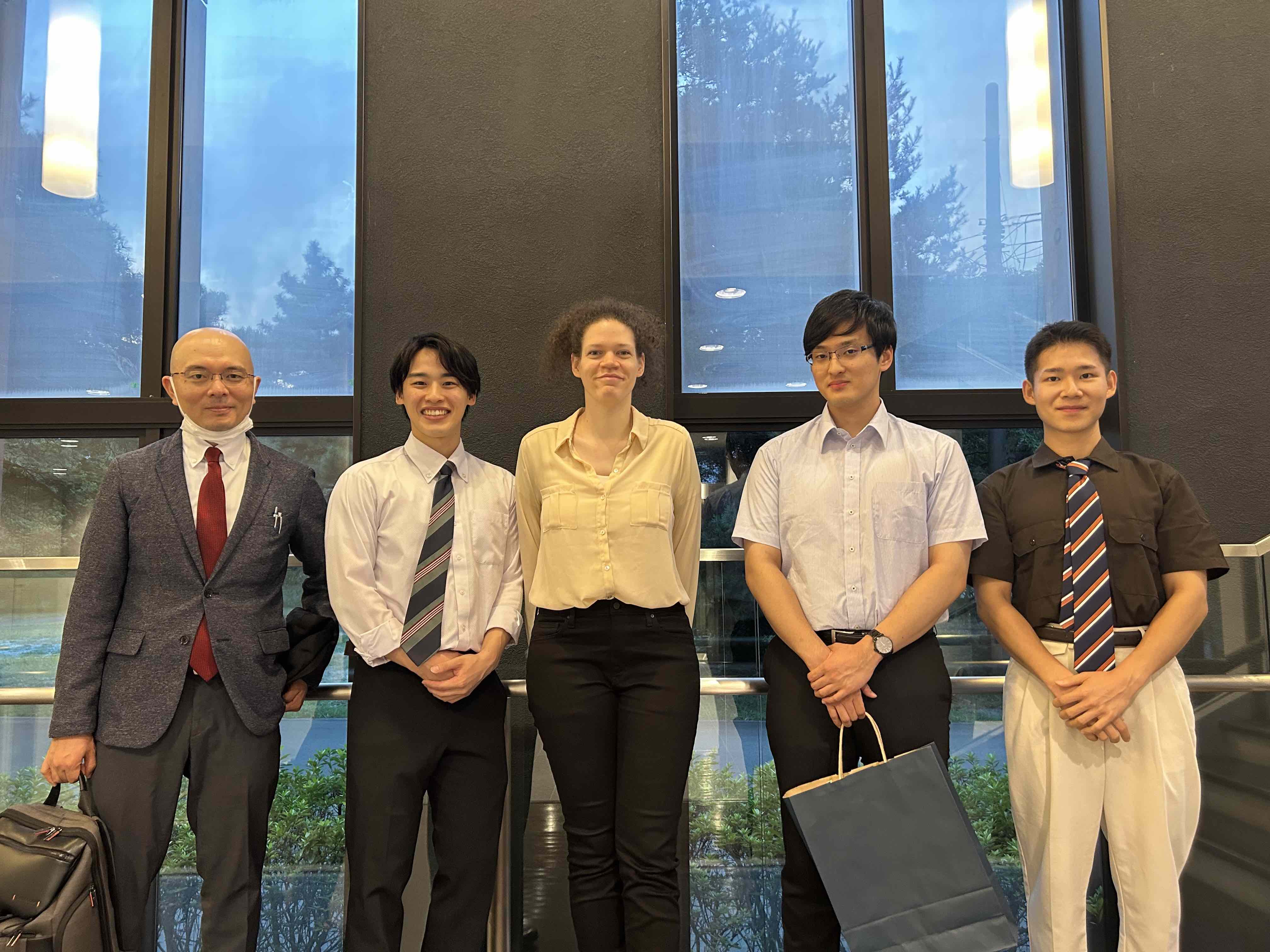


2021年度 Boeing Summer Seminar
2021年度の Boeing Summer Seminar も前年に引き続きオンラインで開催されました.名古屋大学からは3名のチーム(前期課程1年生,学部4年生,3年生)で参加しました.
2020年度 Boeing Summer Seminar
2020年度の Boeing Summer Seminar は COVID-19 の生協によりオンラインでの開催となりました.名古屋大学からは2名(前期課程1年生)のチームで参加し, "Policy to prevent the spread of infectious disease during air travel and to encourage people to travel safely" というタイトルで発表しました.
2019年度 Boeing Summer Seminar
2019年度の Boeing Summer Seminar は Centrair 中部国際空港で開催されました.名古屋大学からは5名(学部3年生)のチームで参加し, "NLRA –New Life of Retired Airplane–" というタイトルで,引退後の航空機の利用方法についての提案を発表しました.

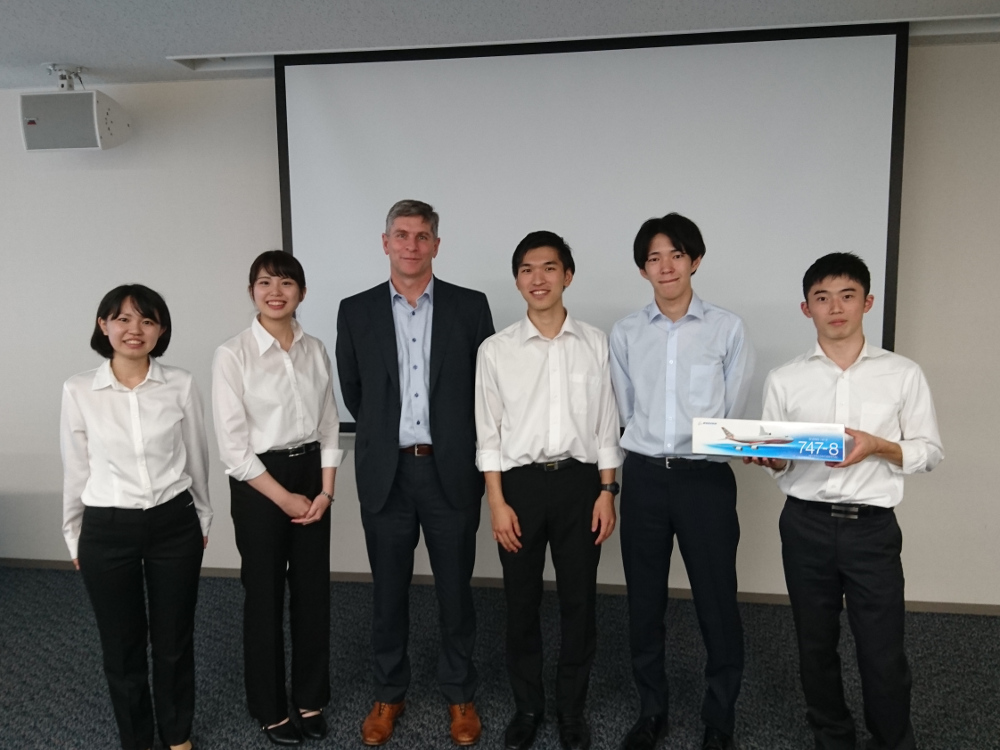
2018年度 Boeing Summer Seminar
2018年度の Boeing Summer Seminar は東北大学で開催されました.名古屋大学からは10名(学部3年生9名,4年生1名)のチームで参加し, "Windowless Airplane and Navigation Plans" というタイトルで,窓なし航空機とその運行についての提案を発表しました.


2017年度 Boeing Summer Seminar
2017年度の Boeing Summer Seminar は東京大学で開催されました.名古屋大学からは2名(学部3年生)のチームで参加し, "AEROS (Automated Efficient Rail Ordering System)" というタイトルで,機内での飲食物の注文と提供の自動化についての発表を行いました.

2016年度 Boeing Summer Seminar
2016年度の Boeing Summer Seminar は金沢工業大学で開催されました.名古屋大学からは5名(博士後期課程1年生1名,学部3年生4名)のチームで参加し,"Optimizing Airline Punctuality by Increasing Aircraft Availability" というタイトルで,定時運行率を向上させるためのアイディアを技術的な面と管理的な面から発表を行いました.

■ 学生プロジェクト支援
Boeing 社から頂いた Grant を用いて,学生が主体となって発案,計画する航空宇宙工学に関連するプロジェクトに対して支援を行っています.原則として,プロジェクトリーダは,機械・航空宇宙工学科(旧 機械・航空工学科),機械システム工学専攻,マイクロ・ナノ機械理工学専攻,航空宇宙工学専攻に在籍する学部生・大学院生とします.


2023年採択プロジェクト
- ハイブリッドロケットの製作および打ち上げ
代表:井坂 晴樹(機械・航空宇宙工学科3年) - CanSat プロジェクト
代表:渡邉 昇(機械・航空宇宙工学科3年) - AirCraft 独自の機体をさらに向上させる!
代表:菅野 遼太郎(機械・航空宇宙工学科2年) - 回転前縁を用いた航空機主翼の高迎角での空力性能改善手法の実証実験
代表:児玉 遼太朗(機械・航空宇宙工学科3年) - 日本唯一 4 輪インホイールモーターEV レーシングカー開発
代表:福岡 平士朗(機械・航空宇宙工学科4年)
※ 所属は申請時
2022年採択プロジェクト
- CanSat プロジェクト
代表:中村 涼真(機械・航空宇宙工学科2年)
報告会発表資料 - 飛行ロボットコンテスト出場機体の開発
代表:中村 亮介(航空宇宙工学専攻 博士前期課程1年)
報告会発表資料 - 4輪インホイールモータEVフォーミュラカーにおける空力開発
代表:福岡 平士朗(機械・航空宇宙工学科3年)
報告会発表資料 - 『Fomalhaut型』の機体を遠くに飛ばす!
代表:高見 晃平(機械・航空宇宙工学科2年)
報告会発表資料 - ハイブリッドロケットの製作及び打ち上げ
代表:飯田 和大(機械・航空宇宙工学科3年)
報告会発表資料
※ 所属は申請時
2020年採択プロジェクト
- 4輪インホイールモータ EV における空力開発
代表:小川 海渡(機械・航空工学科 機械システム工学コース 4年) - 飛行ロボットコンテスト出場機体の開発
代表:黒田 和秀(機械システム工学専攻 博士前期課程1年) - NAFT NRDハイブリッドロケット制作・打上
代表:宮﨑 海杜(機械・航空宇宙工学科2年)
※ 所属は申請時
2019年採択プロジェクト
- 4輪インホイールモータ EV における空力開発
代表:中野 壮毅,機械・航空工学科 航空宇宙工学コース4年
報告会発表資料 - NAFT NRD ハイブリッドロケット製作・打ち上げ
代表:澁井 七海,機械・航空宇宙工学科2年
報告会発表資料
※ 所属は申請時
2018年採択プロジェクト
- EV フォーミュラカーにおける空力開発
代表:中野 壮毅,機械・航空工学科 航空宇宙工学コース3年
報告会発表資料 - NAFT NRD ハイブリッドロケット制作・打ち上げ
代表:鬼淵 駿介,機械・航空工学科 航空宇宙工学コース2年 - Zephyranthes(人力飛行機制作)
代表:齋藤 真,機械・航空工学科 機械システム工学コース2年
報告会発表資料 - 飛行ロボットコンテスト出場機体の開発
代表:黒田 和秀,機械・航空工学科 電子機械工学コース3年
報告会発表資料 - 革新的跳躍機構を有したローバーの開発
代表:冨田 柊人,機械システム工学専攻 博士前期課程1年
※ 所属は申請時
2017年採択プロジェクト
- EV フォーミュラカーにおける空力開発
代表:高木 新,機械・航空工学科 機械システム工学コース4年
報告会発表資料 - NAFT NRD ハイブリッドロケット制作・打ち上げ
代表:加藤 匠,機械・航空工学科 航空宇宙工学コース3年
報告会発表資料 - 飛行ロボットコンテスト出場機体の開発
代表:黒田 和秀,機械・航空工学科 電子機械工学コース2年
報告会発表資料 - 革新的跳躍機構を有するローバーの開発
代表:山崎 匠,機械システム工学専攻 博士前期課程1年
報告会発表資料
※ 所属は申請時
2016年採択プロジェクト
- フォーミュラカーにおける空力パーツの開発
代表:米田 一紀,機械・航空工学科 機械システム工学コース3年
報告会発表資料 - NAFT CanSat Project
代表:横尾 颯也,機械・航空工学科 航空宇宙工学コース2年
報告会発表資料 - NAFT Rocket Development
代表:加藤 匠,機械・航空工学科 航空宇宙工学コース2年
報告会発表資料 - 自走ローバーの開発及び大会出場
代表:辻 輝,機械・航空工学科 航空宇宙工学コース4年
報告会発表資料
※ 所属は申請時
2015年採択プロジェクト
- Aether project
代表:赤理 光,機械・航空工学科 機械システム工学コース2年
報告会発表資料 - 国内スペースバルーン打ち上げ
代表:桑村 航矢,機械・航空工学科 航空宇宙工学コース3年
報告会発表資料 - NAFT Rocket Development
代表:冨田 柊人,機械・航空工学科 機械システム工学コース2年
報告会発表資料 - 新しい概念の飛行ロボットの開発と実践
代表:石原 潤一,航空宇宙工学専攻 M1)
報告会発表資料 - フォーミュラカーにおける流体解析を用いた開発
代表:西尾 俊亮,機械・航空工学科 機械システム工学コース4年
報告会発表資料 - 種子島ロケットコンテスト2015に向けた CANSAT 製作および本戦出場
代表:藤田 涼平,機械・航空工学科 航空宇宙工学コース4年
報告会発表資料
※ 所属は申請時
